『海紀行』人とまちを支える港を訪ねて

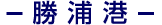

漁業と観光との融合次世代の港町形成に挑む
漁協の荷捌所は早朝から昼近くまで続くセリ市で活気にあふれている。無数のマグロが整然と並び、計量され次々と値がつけられていく。マグロの間を縫うように漁師や仲買人たちが行き交っている。300kg近い大物は別のコーナーに悠々と控えていた。魚というより「肉」というイメージが強くなる。尾を断ち落としたその断面からマグロの質がわかる。ピンク色が淡くなるほど脂が乗って美味いという。屈み込んで吟味する仲買人たちの目は真剣そのものだ。荷捌所の周囲は通路になっていて、観光客がセリの様子を見ることができるようになっている。訪れた人達は所狭しと並べられたマグロに圧倒されていた。近畿最大の遠洋漁業基地、勝浦ならではの風景だ。
しかしながら平成12年の勝浦漁協の水揚量は決して芳しい結果ではなかった。お話しを伺った勝浦漁業協同組合の丸山一郎総務部長は「全国的に有名になった勝浦のマグロですが、最近は厳しい状況が続いていますね」と話す。昨年度の水揚量は15,928t、前述の平成5年度の漁獲高と比較するとその厳しさがうかがえる。12〜13年程のサイクルで大漁の時期が巡ってくるとも言われているが、マグロの生態は未だに不明な点が多く残されているという。後継者不足、消費の落ち込みなど地域が抱える問題も少なくない。そのためアワビなどの種苗放流も行われており、「獲る漁業」のみならず「育てる漁業」に寄せられる期待も大きい。「漁業と観光の融合が町全体の振興に不可欠と考えています。行政と漁協、さらに市民との対話の中から次世代の町の姿を模索しているところです」という丸山部長の言葉が心に残った。
海の果てに新天地を求めて果敢に船を出す海洋民族
千年以上もの昔、那智の浜から荒海に船出した多くの行者たちがいた。厳しい修行を積んだ僧たちはその締めくくりとしてこの「補陀洛渡海」という宗教儀式に臨んだという。この伝承を伝える補陀洛山寺を管理されている瀬川伸一郎さんにお話しを伺った。「わずかな食糧とともに小船に乗りこみ、外に出られないよう屋形を釘付けされ、西方浄土に向け沖に流されたそうです。この渡海は868年の慶龍上人に始まったと伝えられています」。渡海は11月の北風の吹く日の夕刻を選んで行われた。補陀洛山寺本尊の前で秘密の修法を終えた僧は、どよめく観衆に見送られ、今も残る一ノ鳥居をくぐり浜に出た。渡海は享保年間まで続けられ、それまでに補陀洛を目指した者は140人を数えた。「一説によると『補陀洛』とは上海の舟山列島を指しているとも言われています。いずれにしても目の前に広がる海の向こうにある常世の国、不老不死の地に対する深い憧れがあったのかも知れませんね」と瀬川さんは那智の浜に目を向けた。
時代を隔てて明治期にも大海の果てに新天地を求めた人々がいた。ボタンの原料となる真珠貝を採取するために遠くオーストラリアの北、アラフラ海にまで出漁した漁師たちだ。30m以上素潜りで貝を採る仕事は、収入は多かったものの死と隣り合わせの危険な仕事であった。にもかかわらずこうした「海の出稼ぎ」は戦後まで続けられたという。この他にも紀州はアメリカ、フィリピン、カナダ、ブラジル等に移住した渡航者を数多く輩出している。彼等は漁業だけではなく商業、工業に従事し、世界をまたにかけて活躍した。
深い山が迫る熊野灘一帯の人々には、茫洋と広がる海に果敢に挑む海洋民族的な気質が感じられる。

勝浦湾にはその形からライオン島、鶴島と呼ばれる大小130もの巨岩珍岩でできた島々が浮かぶ。写真のラクダ岩周辺も遊覧船が巡る人気スポットだ(写真:那智勝浦町)

「マグロばかりではなくサンマも有名なんですよ」勝浦漁協の丸山総務部長

尾を切り落としたその断面がマグロの質の、ひいては値段の決め手となる

マグロの水揚高では全国で5本の指に入る漁業基地の勝浦港。活気に満ちたセリは年間を通じて行われている

室町時代に描かれた「那智曼陀羅」。船に乗り込む上人と手を合わせて見送る人々の姿や渡海船が見える(写真:那智勝浦町)

補陀洛山寺はその名のとおり補陀洛渡海の中心的存在。渡海に使用された船板や僧たちの墓が残されている

王子浦から見た勝浦港。熊野の山が迫る勝浦は新天地を求めて多くの海外渡航者を輩出した

「渡海は後々水葬という葬儀の形式をとるようになったようです」補陀洛山寺の瀬川伸一郎さん



