名作が生まれた港
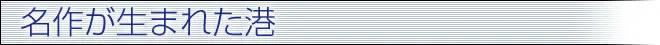
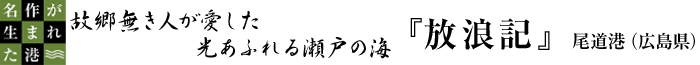

尾道の趣ある風情が多くの作家の創作意欲を刺激した
放浪記 Hourouki

作・林芙美子。第一次大戦後の、不況と暗い世相のなか、貧困にあえぎ、「島の男」との恋に破れ、さまざまな職を転々としながらも、たくましく生きる「私」の姿を、当時としては画期的な躍動感ある現代的筆致で描いた自伝的小説。1928(昭和3)年から『女人芸術』に連載された。現在は、後年に書かれた『続放浪記』なども合わせてまとめた定本として、『新版放浪記』が出版されている。本作を原作とした舞台『放浪記』は、女優・森光子の代表作として知られている。
坂と文学と映画の町・尾道
尾道といえば、坂道のある風景が真っ先に思い浮かぶ。ここでは、町の北側にある山が、そのまま瀬戸内海になだれ落ちるような土地柄のため、古くから山肌の傾斜地に民家や寺社などが密集してきた。
入り組んだ細い坂道の石畳の路地と、昔ながらの面影を残す家並み。そして坂道を降りた先に広がる瀬戸の海。ノスタルジックでいながら、なにか「迷宮」を思わせるような尾道の町並みと穏やかな波を見せる海は、今も昔も、多くのアーティストたちの想像力を刺激し、この町を舞台にした文芸や映画などが度々作られてきた。このため尾道は、「坂の町」であると同時に、「文学の町」、「映画の町」として全国的に知られている。
こうした作品群のなかでも、戦前から戦後にかけて、日本の文学界を代表する女流作家として活躍した林芙美子の『放浪記』は、とりわけ尾道の、そして瀬戸の海のみずみずしさを印象付けるものとして記憶されている。しかし、彼女自身は作品の冒頭で、「私は宿命的な放浪者である。私は古里を持たない…したがって旅が古里であった」と記している。芙美子にとって、瀬戸の海は故郷であったのか、それとも単なる作品の舞台であったのだろうか。

市内の千光寺公園には「放浪記」の一節が刻まれた碑が建てられている
よるべなき家族の安住の地
極めて印象的な書き出しで始まるこの作品は、作者である芙美子の貧しくよるべない暮らしを描いた自伝的小説だ。実際に文芸史家たちは、「明治・大正・昭和の文人のなかでも、彼女ほど貧しく不幸な作家はいないのではないか」と批評している。しかし、一読して感じるのは、それほど不遇で貧しい生活を描いているにも係わらず、作品からは“不思議な明るさ”が感じられることだ。だからこそ、この作品は長年にわたって読み継がれ、今もこの作品を偲んで尾道をはじめとした瀬戸内の港を訪れる人が絶えないのだろう。
林芙美子は1903(明治36)年、北九州市門司で生まれた。行商を営む両親の仕事柄、家族は1つの土地に定住することがなく毎晩が木賃宿での暮らしであり、まさに『放浪記』の冒頭のごとく故郷を持たなかった。
旅から旅の芙美子たち家族が、一時的ながら、ようやくひと処に居を定めたのが尾道だった。今となっては静かな旅情あふれる港町である尾道だが、当時から昭和40年代までは岡山と広島の中間に位置し、海産物の集積地として備後地方では最も栄えた町であったという。
この町で芙美子は、小学校5年から尾道市立高等女学校卒業まで、少女がもっとも感性鋭くある時期を過ごした。この時代の女学校といえば、裕福な家庭の子女が通うものであったが、芙美子は自分で学費を稼ぎながら学問、とりわけ文学の素養を磨いていった。
卒業後、恋人を追って上京した芙美子は恋に破れ、カフェの女給やセルロイド女工、夜店の売り子など職を転々としながら、当時の芸術家たちと恋の遍歴を重ねていく。その様子は、『放浪記』のなかで赤裸々に、しかし明るくたくましく描かれている。

尾道駅にほど近い商店街の入口にある林芙美子像
瀬戸の海を心の古里として
尾道から瀬戸内海を隔てた高松も、林芙美子にはゆかりの深い港町だ。『放浪記』で彼女は、「郷愁をおびた土佐節を聞いていると、高松のあの港が恋しくなってきた。私の思い出に何の汚れもない四国の古里よ。やっぱり帰りたいと思う…」と記しており、作家としての第一歩となった『放浪記』の出版直前、両親が暮らしていた高松を訪れている。
「古里を持たない」と作品の冒頭でいささか気負いぎみに宣言した彼女にとっては、つまるところ尾道や高松に象徴される、波穏やかで陽光きらめく瀬戸内海こそが、本当の「故郷」だったのかもしれない。
「海が見えた。海が見える」
傷心を癒すがごとく、瀬戸内の港に帰る様子を、彼女はこう記す。故郷を持たない旅人を迎えた瀬戸の海は、芙美子が生きた時代も今も、変わることなく穏やかな姿で広がっている。

「おのみち文学の館」に再現された林芙美子の書斎

林芙美子が幼少時代に通った土堂小学校